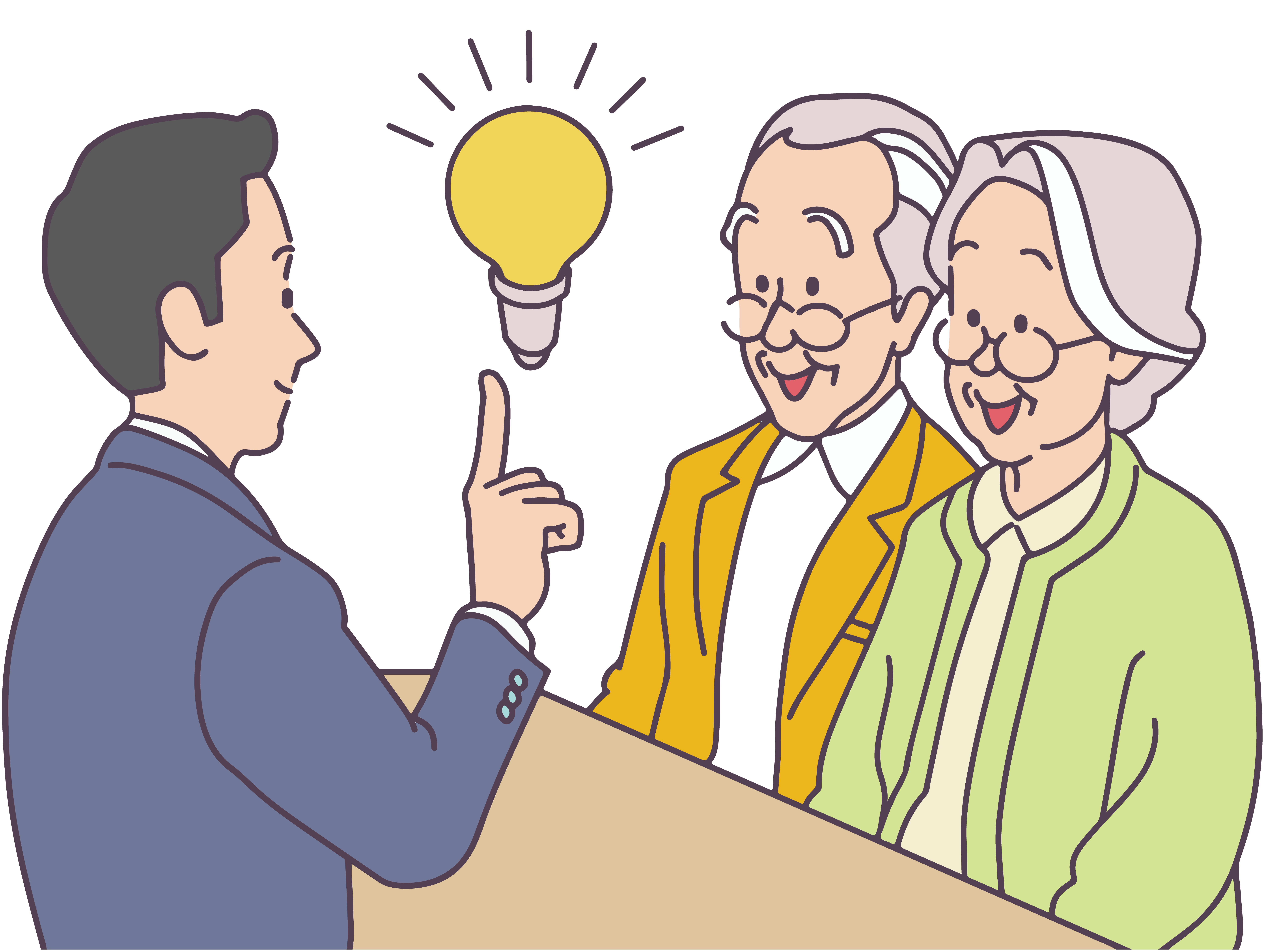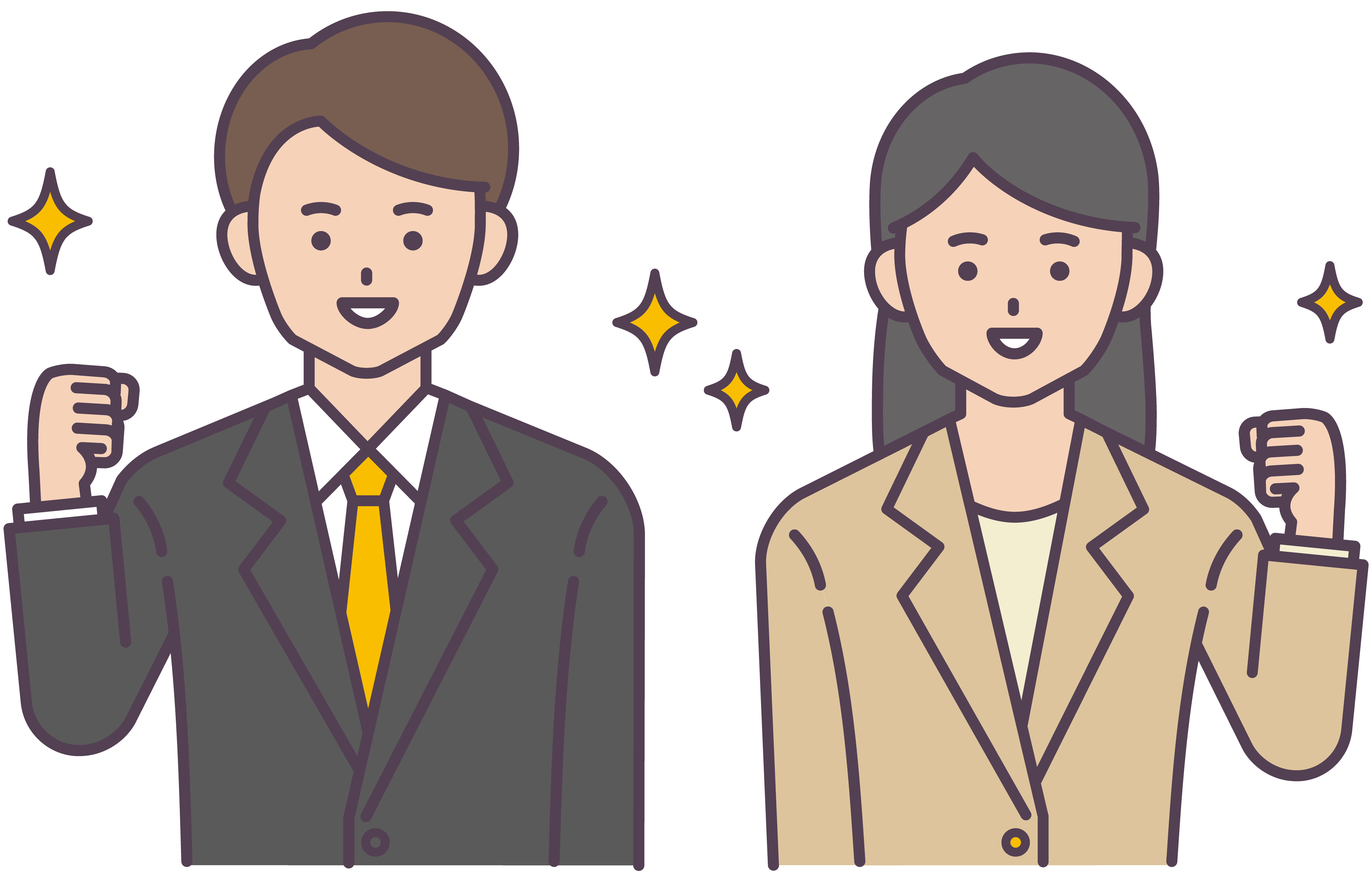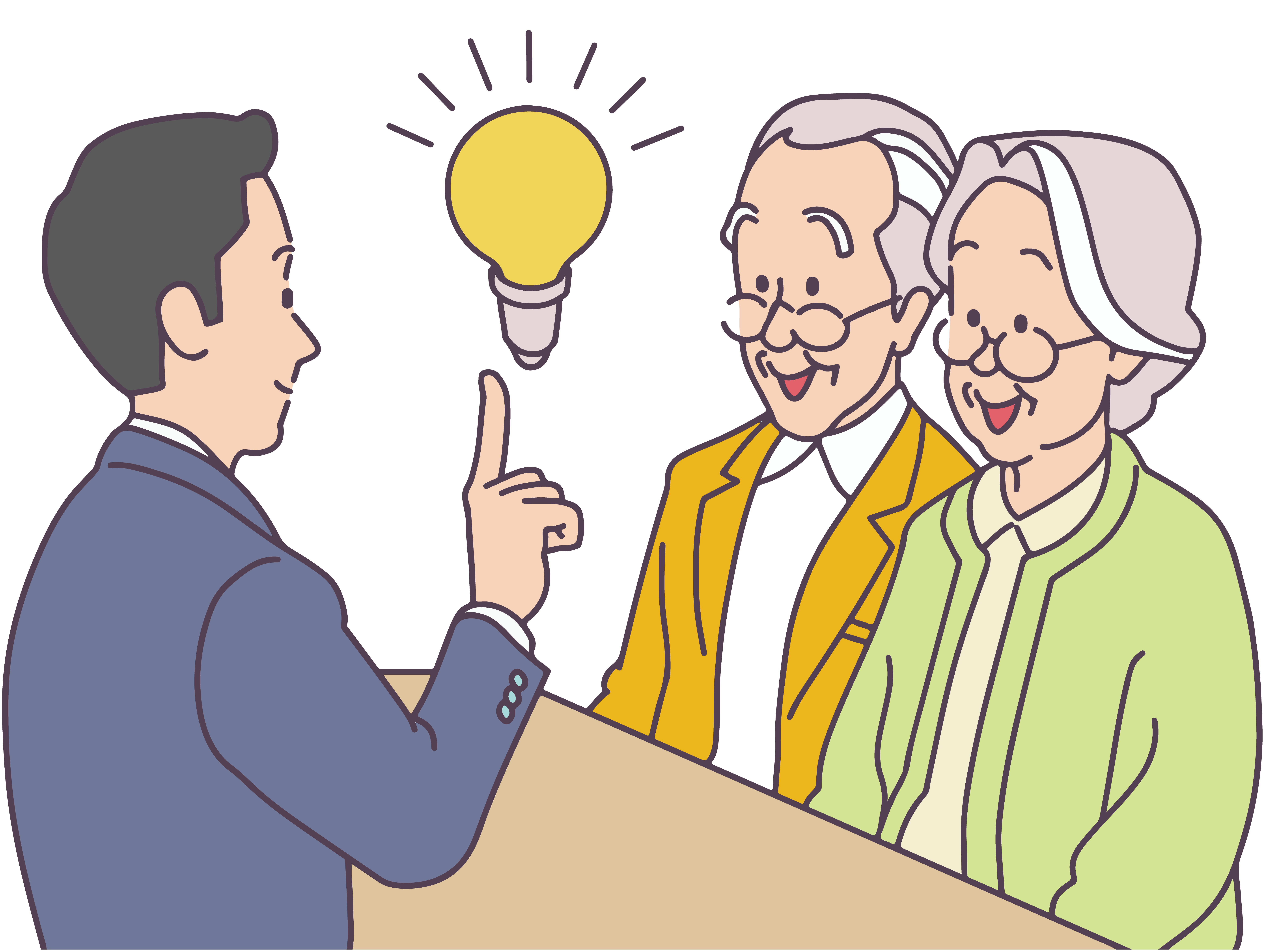
保険は種類がたくさんあってよくわからない、という方もいらっしゃるかも知れません。
生命保険、死亡保険、医療保険、がん保険など
生命保険を大きく分けると4種類に分類されます。
生命保険は大きく分けて主に4種類
- 死亡や後遺障害など、残されたご家族や自分自身の重度の後遺障害に備える死亡保険
- 病気やケガなど病院でかかる手術代に備える医療保険
- 子供の将来など受験や進学などに備える学資保険
- 老後の貯蓄など余裕をもった生活をするための、養老保険、個人年金保険、介護保険など
生命保険と聞くと死亡保障の事と思う方もいるかもしれませんが生命保険は全体の事をさし
生活する中で予測できない出来事に少しでもお金の心配をしないで済むよう備えるのが上記の4つになります。
この4種類が混ざった商品が多いのでよくわからなくなってしまいます
宮崎保険ではこれらの4種類を分かりやすくなるようになるべく個別にお客様のニーズに合った商品を販売いたします。
あと、気になるのは保険料です。どれくらい保険を掛けるかや期間は人によって変わりますが社会保険で加入している健康保険や国民健康保険、
厚生年金や国民年金で足りない分の補填にしなくてはなりません。
保険料が気になる方の為保険料シュミレーションもご用意しております。
「万一のことが起きた場合でも、残された家族が安心して暮らせるようにしたい」
「まだ子どもも小さいので、困らないように教育資金を備えておきたい」
「購入した住宅のローンがまだ残っているので、万一の際にも困らないようにしたい」など
万一の事があったときに、残された家族の経済的な支えとなってくれるのが「死亡保険」です。
まずは死亡保険の基本を理解し、「誰のために」「何のために」備えるのかを考えてみましょう。
また、死亡保険にはいくつかの種類・特徴がありますので、それぞれに合った保障を知ることが大切です。
死亡保険の種類は主に4つ
死亡保険とは、先にも触れたとおり、死亡や高度障害など万一の場合に、
残された家族の経済的な負担を減らして、その生活をサポートしてくれる保険になります。
死亡保険に加入すると、亡くなられた場合や、病気やけがによる高度障害状態になった場合に保障が受けられます。
また特約をつけることで病気や、思わぬケガにも備えられるタイプもあります。
死亡保険の主契約の種類は主に4つあります。
- 定期保険
- 終身保険
- 養老保険
- 収入保障保険
それぞれの保障内容に特徴がありますが、まず「どれが自分に向いている保険なのか」をしっかりと理解し、選ぶことが大切です。
では分かりやすくそれぞれの特徴を見てみましょう。
「生命保険について実際にどんなタイミングで加入したらよいかというと、結婚、出産、入学、就職、マイホーム購入、
転職、定年など「ライフサイクルが大きく変わる節目」は特に適したタイミングと言えます。
生活環境に大きな変化が起きると、これまで入っていた保障では足りなかったり、多すぎたり、保障内容と生活環境に
ズレが生じてしまうことがあります。
ライフサイクルに大きな変化があると……
- これまではいらなかった保障が、必要になる
- これまで必要だった保障が、不要になった
- これまでの保障の大きさでは足りない、または多すぎる
例えば、「子どもが社会人になったので、これまでの手厚い保障が不要になった」、
「子どもが生まれるので将来の教育資金を考えたい」など、保障を考える時は少なからず何かの変化がある場合が多いです。
生命保険の中で、不慮の事故や病気などで万一亡くなったり、高度の障害状態になった場合の備えとしての役割をもつのが「死亡保険」です。
この死亡保険も実はいくつかの種類があります。色々な種類があって頭がいっぱいになりそうですが、
ここでも少し整理をしながらご自身に合った保障の選び方をご紹介したいと思います。
死亡保険を選ぶときの手順
死亡保険の選び方は、分かりやすくまとめると以下の「1~3」の流れになります。
- 「何のために(誰のために)」保障が必要なのか、目的を確認する
- 「保障が必要な期間」と「保障の大きさ」を確認する
- 自分のニーズに合う、死亡保険の商品を選ぶ
02
「保障が必要な期間」と「保障の大きさ」を確認する
目的がはっきりしたら、次は保障が必要な「期間、保障の大きさ(保障額)」について考えていきましょう。
ポイント:保障が必要な期間についての考え方
1で確認した「何のために(目的)」が、保障を必要とする期間を割り出すためのポイントになります。
例えば、
- 「子どもが成長するまで(独立するまで)」の間
- 「退職時期まで」に老後の資金を準備しておきたい
- 葬儀費用などを「生涯」において準備しておきたい
など、「何のために」が明確になると、どのくらいの期間を備えておかなければいけないのかが明確になってきます。
ポイント:必要な保障の大きさを計算する方法
期間がきまると、その期間内でいくらくらい備えておかなければいけないのかという「万一のときの保障の大きさ」の目安を算出することができます。
その目安の計算方法は、
「A.必要な費用」-「B.国・会社から受けられる公的・民間の保障額」です。
- A.必要な費用
- 家族の生活費・子どもの教育資金など「目的」「期間」より算出した額
- B. 国・会社から受けられる公的・民間の保障額
- 公的保障(遺族年金など)や、企業からの死亡退職金などご自分での備えとは別に受けることのできる金額
目的が決まれば備えるべき期間が決まり、その間に必要な保障額を出すことができます。
そこから、国や会社から受けられる保障などを差し引いた金額が、備えなければいけない金額の目安になります。
貯蓄額なども踏まえて考えていくと、より現実的に備えなければいけない金額を出すことができます。